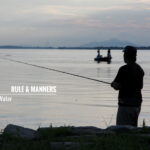INDEX
日本に数多くある湖沼や河川では多種多様な生物が生息し、生命活動を営んでいます。しかし一方で、魚がいなくなってしまったり、もともと魚がいないといった場所も存在します。
一体どうして「魚がいない」湖や川があるのか、詳しい環境やその理由について深掘りしてみましょう。
魚が棲まないといわれた「十和田湖」でヒメマスの養殖に成功

まず、湖において魚が生息していない大きな要因に挙げられるのが「カルデラ湖」の可能性。カルデラとはスペイン語で「なべ」を意味し、火山の噴火によって大きく丸く凹んだ場所のことを表します。そこに雨水や湧き水が溜まり、深い湖になったものが「カルデラ湖」。カルデラ湖は周囲を急峻(きゅうしゅん)な山々に囲まれていることが多く、流入する水や栄養分などの量が少ないため、魚が生息しにくいといわれています。
そんなカルデラ湖の代表格が、秋田県と青森県にまたがる「十和田湖」。魚が棲まないとされていた十和田湖でしたが、明治36年にヒメマスの養殖のため、稚魚が放流されました。明治38年にはヒメマスの群れが湖岸へと戻り、ヒメマスの生育定着に成功。今では「十和田湖ひめます」として地域団体商標に登録され、十和田湖の特産品になっています。

中性から傾いた水質や酸性雨が、魚がいなくなる原因をもたらす…
水質も魚の生息には大きく影響します。湖沼や河川などの淡水では、中性にあたるpH7が魚にとって最も生息しやすい環境。pH(ペーハー)は水の「酸性」と「アルカリ性」の度合いを表す値で、中性のpH7より小さい値になればなるほど酸性が強く、逆にpH7より大きな値を示すとアルカリ性が強いことを表します。酸性やアルカリ性のどちらに傾きすぎても、魚の致死率は高まることに。

また、「酸性雨」も魚がいなくなる原因の1つです。酸性雨は石油や石炭を燃やした際に発生する二酸化硫黄や窒素酸化物が、大気中で硫酸や硝酸に変わり、それが雨や雪として降ってきたもの。また、風に乗って地上に降りてくる場合もあります。
酸性雨の影響として、北欧では湖や川が酸性化した結果、サケの仲間が姿を消してしまう事態が発生。酸性の汚染物質を含んだ雪が、春になって溶けだしたことで、川や湖が酸性化してしまったことが原因でした。日本でも水質が微酸性に変化しただけでヒメマスが産卵をやめたとの報告も。中性に近い微酸性であってもヒメマスにとってはかなり大きく影響することが分かっています。
栄養は少なすぎても多すぎても魚は育ちにくい

十和田湖は底が見えるほど透明度が高いことで有名な湖です。実は、この十和田湖のような透明度の背景にあるのが、湖の水に栄養分が少ないという事実。このような湖は「貧栄養湖」と呼ばれ、栄養分が少ないことでプランクトンや藻が繁殖しにくい環境にあります。そのため、エサとなる生物も少なく、それらを食べる魚も育ちにくい場所といえるでしょう。

反対に、栄養が過剰すぎる状況も魚がいなくなってしまう一因。湖沼には生物が生息するために必要な栄養素が含まれています。この栄養素が増えることで植物プランクトンの量が変化し、貧栄養状態から富栄養状態へ変わる「富栄養化」が起こります。
富栄養化では、特定のプランクトンや有害藻類が大量に繁殖する事態に。結果、水質の透明度が下がり、光合成を阻害してしまうことで水中の酸素は減少。最終的には、水質汚染や魚の死滅を招くことにつながってしまうのです。
1人1人の取り組みが水質環境を守る

川では、産業排水や生活排水の流入による環境汚染や水質悪化も問題視されています。水質汚染により水棲生物が減少し、生態系にまで深刻な影響を与えることも。
一方で、環境を改善したところ魚が戻ってきたケースも多くあります。たとえば、昭和の終わりごろから下水道が整備され、合併浄化槽が普及した会津若松市では、これまで川に垂れ流しにされていた生活排水が適切に処理されるようになりました。その影響は大きく、生活排水で汚されてしまい一度は魚がいなくなった市街地を流れる川にも、生き物が見られるようになりました。

浄化設備のような大きな整備以外にも、個人として川を汚さないためにできる取り組みはたくさんあります。「食べ残しや食用油を排水口に流さない」「水路にゴミを捨てない」ことなどが挙げられるでしょう。湖沼や河川の豊かな自然環境を守るためにも、私たちの日々の生活を今一度振り返ってみることが大切かもしれません。