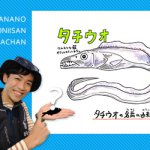ウナギをはじめとする、細くてにょろにょろしている魚たち。名前を知っていても、漢字は知らないという人は多いのではないでしょうか。
今回は、にょろにょろ系の魚の漢字表記をご紹介。漢字の由来や魚の特徴についても触れていくので、ぜひチェックしてくださいね。
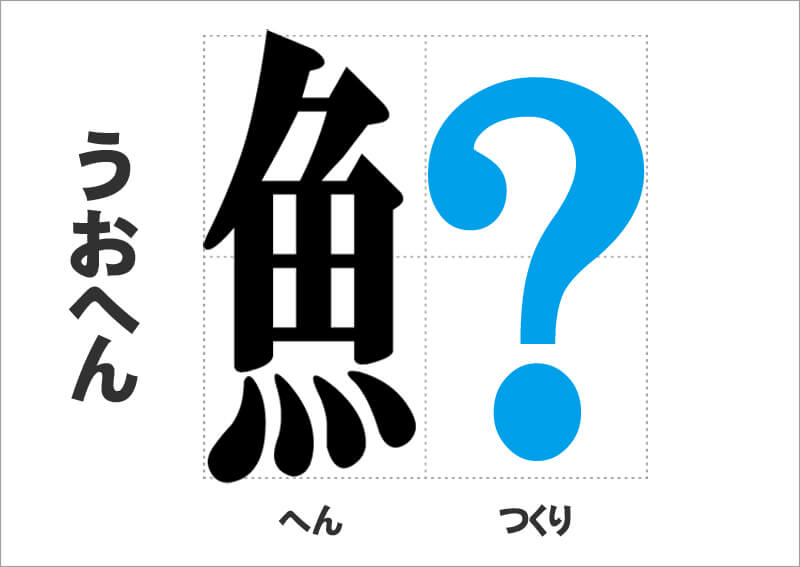
にょろにょろ系の代表格「ウナギ」と「アナゴ」

まずは、にょろにょろ系の代表格である「ウナギ」から見ていきましょう。漢字表記は「鰻」と書き、昔は「むなぎ」と呼ばれていました。諸説ありますが、ウナギの名前が登場する記述で最も古いのは、「万葉集」の和歌だといわれています。
名前の由来についても複数あり、身を「ム」と読んで、ウナギの細長い身体を「ムナガ」と読んでいたのが変化して「ムナギ」となった説。ウナギの胸の部分が黄色っぽいことから、「胸黄(むなぎ)」と呼ばれて変化した説があります。ほかにも細長い身体が棟木(むなぎ)に似ている点に由来して「ムナギ」となった説も…。最終的に「ウナギ」と呼ばれるようになったのは12世紀ごろだそうです。

気になる漢字の由来ですが、ウナギの漢字に入っている「曼」には、つや・細長いという意味が。そのため、細長く、つやがあるウナギを表す字として「鰻」が誕生したといわれています。
ちなみに寿司や天ぷらで人気の「アナゴ」も、同じ「ウナギ目」に部類される仲間。こちらは魚へんを使わず「穴子」と表記されます。アナゴの名前は、文字通り砂泥地の穴に潜り込む習性から名付けられました。

ミミズを意味する漢字を付けられた「ドジョウ」

同じくにょろにょろ系の魚として有名なのが「ドジョウ」。ドジョウはウナギに見た目は似ていますが、コイ目ドジョウ科に分類される淡水魚のため種類が異なります。ちなみにウナギとドジョウにはウロコがありますが、アナゴにはウロコがありません。

ドジョウの漢字表記は「鰌」。つくりの「酋」はミミズを表す言葉で、ミミズのように泥のなかに棲む魚という意味で、「鰌」という漢字が当てられました。
見た目から名付けられた「ナマズ」

「ナマズ」はナマズ目ナマズ科に分類される淡水魚で、ウナギやドジョウとは違った分類の魚です。ウロコがなく滑らかな表面をしているため「ナメ」という音が当てられ、泥や土を意味する「ズ」の音が合わさり「ナマズ」の呼び名に。「ズ」は頭の意味もあるとされ、皮膚がスベスベしている大きな頭の魚という意味で呼ばれ始めたともいわれています。

ナマズの漢字は「鯰」と表記。「念」はねばるという意味で、ナマズのネバネバした身体の特徴から「念」が用いられたという説があります。
強面の魚として有名な「ハモ」と「ウツボ」
にょろにょろ系の魚には、「ハモ」や「ウツボ」のような、見た目が強面の魚も。京都や大阪で夏の風物詩として食べられている「ハモ」は、ウナギ目ハモ科に分類されるウナギの仲間です。

ハモの名前は、よく噛みついてくる特徴から「喰む」の言葉が変化して「ハモ」になったという説のほか、単に味が美味しいため「食む」から「ハモ」になったという説もあります。

ハモは「鱧」という漢字で表記しますが、「豊」には「曲がる」や「黒い」という意味があるため、ハモの漢字に用いられたよう。川から上げても、皮膚呼吸のみで24時間以上生き続ける生命力の強さにちなんで「豊」が使われたという説もありました。

ハモと同じくいかつい見た目が特徴のウツボは「鱓」と表記。ウツボはウナギ目ウツボ科で、こちらもウナギの仲間です。長い身体が矢を入れる「空穂(うつぼ)」という道具に似ていたため、ウツボと呼ばれるようになったといわれています。ほかにも昔の言葉で空洞を意味する「うつほら」が、岩穴に潜むウツボの習性を連想させるため名付けられたという説もあります。

漢字については、ウツボの見た目から取り入れられています。ウツボの身体は平たいフォルムのため、平らを意味する「單」が使われました。ウツボがタウナギに似ている点から、タウナギを意味する「單」が用いられたという説もあります。
魚の見た目や習性など、さまざまな意味が込められている魚へんの漢字。日常で魚にまつわる漢字を見かけた際に、漢字の意味を考えると新たな発見にもつながりそうですね。
※本文の漢字の成り立ちや名前の由来は諸説あるうちの一部です。ご了承ください